ブログを書いてみよう!と思って書き始めた去年11月ごろ。
その頃は、自分のこと、からだのことについての気づきがたくさんあり、そういうことを書いていこうと思っていましたが、
ブログ慣れしていないというか、そもそも自分を「表現」することが下手なので、
「ブログで書く」ということ、「誰に読まれるかわからないところに文章を書く」ということに、ものすごく気負いがあり、
一つの投稿にすごく時間がかかりました。
「とりあえず書く」ことを目標に記事を書きためていったものの、いざ投稿するとなると「ちゃんとした文章かどうか」が気になり、修正したり見直したりしている内に、結局投稿できずにいる下書きだけが増えていったのでした。
そうこうしている内に、引きこもり病弱人間に、ありがたいことに旅立ちの機会がやってきて、12月は高知県に行くことになりました。
その間は全くブログを書くことができませんでした。
そんなこんなで、帰ってきて1月、「よし、ブログを再開だ!」と、下書きをほじくり返し、投稿しようとPCの前に座りました。
が、書けないし、まとまらない…。時間だけがすぎていく…。
こんなことを2~3日して、「こりゃいかん」となり、心機一転、前の続きではなく、新たに文章を書いていくことにしました。
やはり、「その時」書こうとしたものは、「その時」に完成させて投稿して成仏させないと、時間がたって再度いじくって完成させようとしても、何だかうまくいかないのですね。
「今」表現しようと思ったことは、「今」出さないと意味がないのだと、また新たな気づきを得ることができました。
(12月は何だかずっと便秘気味だったのも、うなずけます🤣)
ついついいつもの癖で、「ちゃんとしたものを書かなきゃ」という「ちゃんと病」がでてしまい、完成度というか体裁ばかりを気にしてしまうんですよね。
ブログを書いたことがない初心者が最初から、思うように、良い感じに書けるわけがないのだから、つたなくても未完成でも、とりあえず書いて投稿していきたいと思います。
ホワミル↓も、「ゆるく、楽しくね」って言ってますしね😉

「勘定に入っている」ということ。
今朝はファンである小出遥子さんの著書『教えて、お坊さん!<さとり>ってなんですか?』を読み始めました。
小出さんが、いろんなお坊さんに「さとり」をテーマにインタビューしたものがまとめられた本で、以前から気になっていたのですが、この度ようやく手に入れました。
今日は第一章の藤田一照さんというお坊さんとの対談のところだけを読みました。
藤田さんは東大で心理学を専攻された後、禅道場に入山し得度され、渡米し17年間座禅指導に当たられた、現曹洞宗国際センター所長という、ユニークな経歴のお坊さんです。
この藤田一照さんの第一章は「<つながり>を楽しんでいきること」というタイトルなのですが、<つながり>っておもしろい言葉だな、と改めて思いました。
そして、今日わたしがさらに関心をかきたてられたのは、
「勘定に入っている」という言葉です。
一照さんは、10歳の時に夜空の星を見て「宇宙と、たった一人の僕とが直に対面しているみたいな感じ」という謎の衝撃の感覚を味わったそうなのですが、
一照さんが仏道に入った理由として、
「あの時に見たものとか、抱いた謎の感じっていうのが大事にされている世界にいたいな、っていう思いはあった。そういうことにちゃんと応えてくれるっていうか、勘定に入っているようなところにいたいなって。それで最終的に仏教を選んだっていうのはあるね。」
小出遥子「教えて、お坊さん!<さとり>ってなんですか?」(p.56)
と、語っておられるのですが、
わたしこの「勘定に入っている」「勘定に入れる」という言葉が好きなんです。
「勘定に入れる」とは…
① 計算するものの中に繰り入れる。
(出典:精選版 日本国語大辞典)
…と辞書にありますが、要は、何か対象となるものを「頭数に入れておく」ということだと思うんですよね。
それが帳簿上のことであれ、実際の人の集まりのことであれ、誰かの頭の中のことであれ、数に入れておく。
その対象となる何かに直接働きかけたりすることはなくても、自分のフィールドにはちゃんと置いておく、という感じ。
その、ただ「いるよね」って認識している感じ、認識されている感じが、まさに「つながり」という気がするのです。
「ぼくは、Kさんを勘定に入れた世の中に生きていたい」
わたしは、以前にデイサービス施設で障害者と言われる方に関わっていました。
ある時、施設に関わってくれていた大学生のボランティアの人たちと、障害者と健常者が分断されている社会の現状について話している時に、一人の男子学生が、利用者Kさんとの関係について、
「ぼくは、Kさんを勘定に入れた世の中に生きていたい」と言ったのです。
わたしはそれを聞いて、「Kさんを勘定に入れる」という言い回しを使う彼のセンスにうなってしまったのです。
障害者と健常者は、ほとんど教育の段階で分けられてしまうので、なかなか出会う、共に在る、ということが叶わないのが今の社会の現状です。
出会うとしたら、健常者が障害者用に作られた学校や施設にわざわざ会いに行く、という形になりがちで、それはどうしても特別なことになってしまいます。
しかし彼は、「障害者」というその他大勢ではなく、「Kさん」という、一人の自分と関係を持った人としてのKさんが、特別ではなく、日常の、自分の生きる領域にちゃんといる、そんな世界がいい、ということを表明するために、「Kさんを勘定に入れる」という表現を使っていたのでした。
それ以来わたしは、「勘定に入れる」という言葉が好きになりました。
ちゃんと、いる。
存在している、ということを確認してる。
特別ではなく、空気のようにあたり前にいること(在ること)が、確認しあえていることを、「勘定に入れる」という言葉は表現してくれるので、すごく便利でいい言葉だと思うのです。
そんなことを、藤田一照さんの「勘定に入っている」という表現に触れて、思い出したのでした。
直接何か、肌身に触れて関与しあわなくても、ただいるだけで自ずと関与して、作用してしまっている…
そんな、どうしようもなくある<つながり>を表現する言葉。
「勘定に入れる」って好きだなあと、改めて思いました。
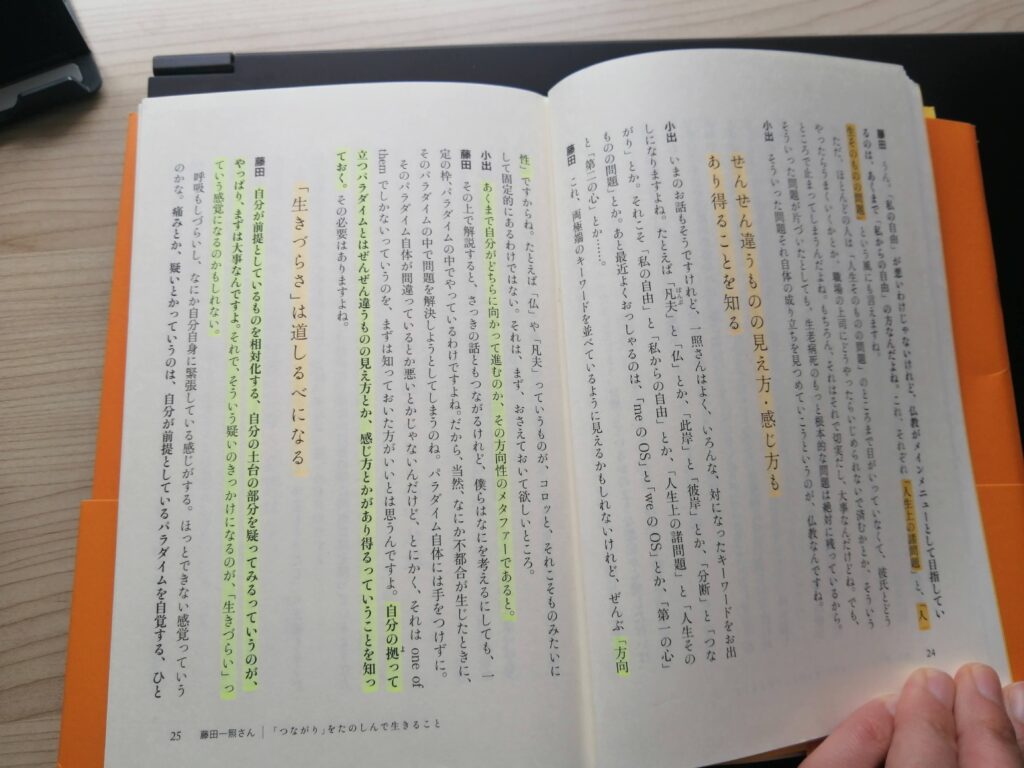
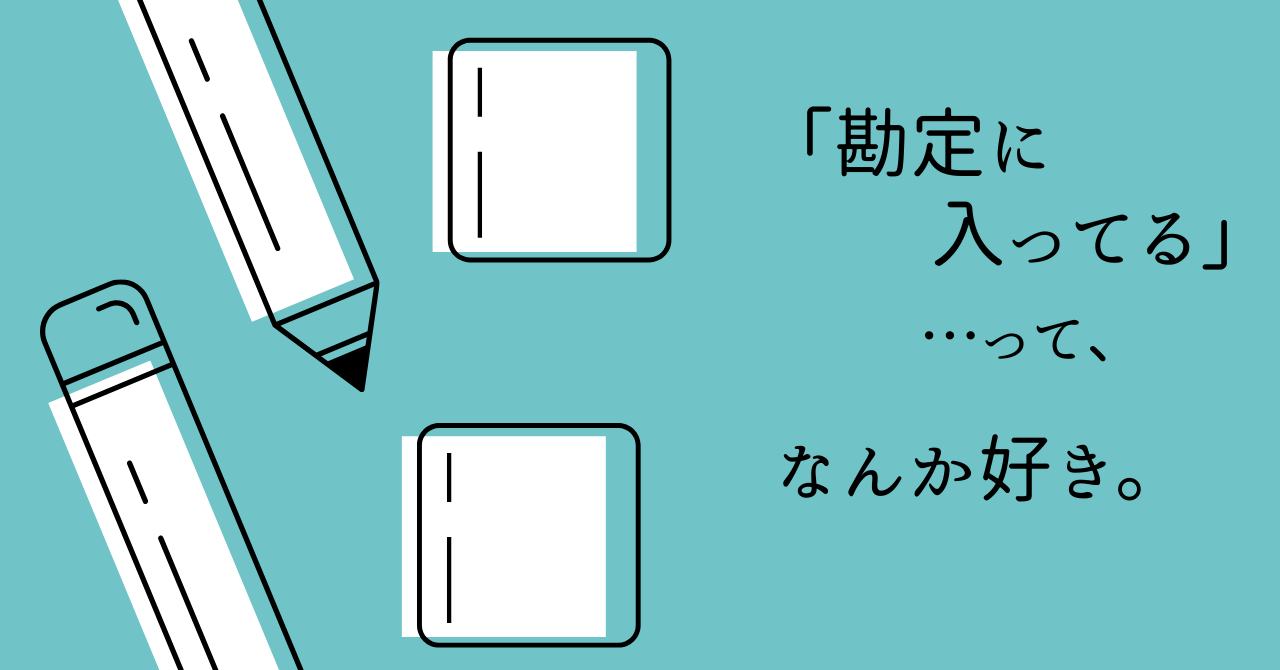

コメント